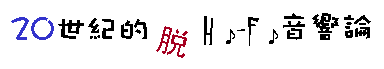
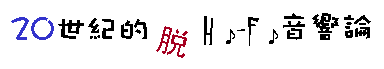
���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R�j
�@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�uEMI�N���j�N���v�́A�A�����J���t�������W�Ń��m�����̃T�u�V�X�e�����č\�z�����̂ɁA�pEMI�̃T�E���h�ɖڊo�߂��I�[�f�B�I���������Ԃ��Ă��܂��B�B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�Ȃ���JBL+Altec��PA�p�X�s�[�J�[�����m�����őg��ʼnx�ɂ͓����Ă܂��B 5)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI�N���j�N��
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y�j�āA���̗ϓցi�����h���j�z �@�p�������Ȃ���A���m��������̉pEMI�Ƃ����Ζ��ɕ�܂ꂽ�悤�ȉ��A����������ۂ��������B�悭�����Ώ�i�Ȃ̂����A���������ɕ������܂����悤�ȁA�X�m�b�u�ȕ��̌��������@�ɂ��A�Ƃ������Ō�܂ł͂����茾��Ȃ��̂ł���B�����C�M���X�ł�Decca�͑S���t�ŁA�Ќ�I�Ńy�`���N�`������ׂ鉻�ϔ��l�B���̗��҂̋ɒ[�ȃT�E���h�̈Ⴂ�䂦�ɁA�u���e�B�b�V���E�T�E���h�͌���Ɍ�����d�˂Ă���悤�Ɏv���B �@�p�������Ȃ���A���m��������̉pEMI�Ƃ����Ζ��ɕ�܂ꂽ�悤�ȉ��A����������ۂ��������B�悭�����Ώ�i�Ȃ̂����A���������ɕ������܂����悤�ȁA�X�m�b�u�ȕ��̌��������@�ɂ��A�Ƃ������Ō�܂ł͂����茾��Ȃ��̂ł���B�����C�M���X�ł�Decca�͑S���t�ŁA�Ќ�I�Ńy�`���N�`������ׂ鉻�ϔ��l�B���̗��҂̋ɒ[�ȃT�E���h�̈Ⴂ�䂦�ɁA�u���e�B�b�V���E�T�E���h�͌���Ɍ�����d�˂Ă���悤�Ɏv���B�@�����ЂƂ̌���́A�C�M���X�̉��y�E���̂��̂ɑ�����̂ŁA�����ɔ�����̉��y��������̉����Ă���悤�ɂ݂���_�ł���B�����������h���Ƃ����A���[�c�@���g�̎��ォ��̈�古�Ɠs�s�ŁA���E���̉��y�Ƃ��W�܂��Ă������y�̓s�ł���B�ӔN�̃n�C�h���͎����̗����ōł��h�_������̂Ƃ��āA�I�b�N�X�t�H�[�h��w����̉��y���m����ɋ����邭�炢�ł������B���������N���V�b�N���y�Ƃ����T�O���̂�18���I�̉p���M�����l���o�����iAncient Musiks�j���̂ŁA�����ł����R���b���⃔�B���@���f�B�A�w���f��������ɑ������A���オ����ɏ]���ČÓT�h�A���}���h�ƃ��p�[�g���[�𑝂₵�Ă������B���̕�����Y���L�^�Ɏc�����Ƃ����̂��A�pHMV�`EMI�̖{���̋��݂ł���B �@���̂��߁A�pHMV�ƌ������R�[�h�ƊE�ł͘V�ܒ��̘V�܂ŁA����Ȍ�����������A�A�����J�̖{��Victor�����ɕ������킹�đ啨�A�[�`�X�g�����^�����̂ɔ�ׁA�pHMV�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɖ��y�Ƃ�����]���邽�߂ɘ^������A����������̂��郌�[�x���ł���B�Ƃ������A�����J�ŐԐF�ƍ��ŃA�[�`�X�g����ʂ��Ă������A�pHMV�ɂ͂����������̂������B�����Ă����ΑS�Ă��т̑т���߂��ꋉ�i�ł���B 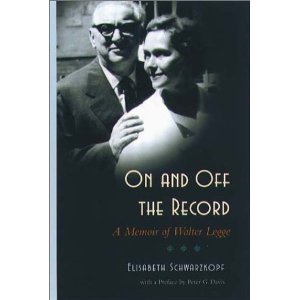 �@�����������R�[�h�}�j�A�̐S�ɂ���ɖ��𒍂����̂��A�啨�v���f���[�T�[�̃E�H���^�[�E���b�O�����N����������Ճ��R�[�h�ŁA���i�����Ȃ����p�[�g���[���s�\�Ő��������Ƃ���Ń����[�X����Ƃ������́B1932�N�̃��H���t�̋ȏW����ɁA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�S�W�A�����ȑS�W�ȂǁA����܂ł̃��R�[�f�B���O�ł͍l�����Ȃ��c��ȃA�[�J�C����z�����ƂƂȂ����B �@�����������R�[�h�}�j�A�̐S�ɂ���ɖ��𒍂����̂��A�啨�v���f���[�T�[�̃E�H���^�[�E���b�O�����N����������Ճ��R�[�h�ŁA���i�����Ȃ����p�[�g���[���s�\�Ő��������Ƃ���Ń����[�X����Ƃ������́B1932�N�̃��H���t�̋ȏW����ɁA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�S�W�A�����ȑS�W�ȂǁA����܂ł̃��R�[�f�B���O�ł͍l�����Ȃ��c��ȃA�[�J�C����z�����ƂƂȂ����B�@���ɂȂ��Ă��A�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̐ݗ��A�J�������A���p�b�e�B�A�J���X�A�����čȂƂȂ����V�����@���c�R�b�v�ȂǑ啨�A�[�`�X�g�����X�Ƀ}�l�[�W�����g���A�㐢�Ɏc�郌�R�[�h���c�����̂����狰�����B�}�[�P�e�B���O�ɒ����Ă��Ĉӌ����Y�o�Y�o�������r�ȂƂ��납��A�Ǎ�ƂŌ|�p���̐l�i�~�P�����W�F���A�|���[�j�Ȃǁj����a���Ē����_��Ɏ��s������A�t�ɐ��̃x�[�g�[���F���@�s�A�m�E�\�i�^�S�W�̎��^�ɂQ�x���s�i�\�������A�M�[�[�L���O�j�������ƂȂǁA���̐l�炵���Ȃ�����k������B�Ƃ������A��O����̑�Ŕ�w�����đ啨�A�[�`�X�g�ƑΓ��ɓn�荇�����̂́A��ɂ���ɂ����̐l���炢�Ȃ��̂ł��낤�B����Ƌ��ɁA1963�N��EMI�𗣂��܂ł�30�N�ȏ�ɓn��L�����A��ʂ��āA�]���̎U���I�ȃp�t�H�[�}���X�ɓO���Ă������R�[�h�Ƃ����}�̂ɁA�|�p���Ɠa������̖��_��^���邱�Ƃ̂ł������т͌v��m��Ȃ��B
�@�����EMI�ɂ����Ċy���݂Ȃ̂��A�e���ɒ��菄�炳�ꂽ�x�ЖԂł̌��n�^���ł���B�����ł͎��R�ȍٗʂŃ��R�[�f�B���O���ł������߁A�ʏ�̖��Ȗ��Ղɂ͊Y�����Ȃ����p�[�g���[���������݂���B����EMI�O���[�v�̋����́A�č����V�̗��v�U���^�Ƃ͈قȂ郍�[�J�����[���d�����Ƃ��낾�낤�B�ƃG���N�g���[���A���p�e�A���C�X�p���H�b�N�X�ȂǁA�Ǝ����ŗD�G�Ș^�����������݂���B �@���m�������̘^����������ƁA�E�B�[���𒆐S�Ƃ��ăt���g���F���O���[�����^�����N���[�́A���炩�ɐ�O����̃}�O�l�g�t�H�����g���Ă���A������킴�킴78rpm�̃��b�J�[�ՂɃ_�r���O�����Ƃ������́B��⍂��̌��������́ADecca�^���ɂ������Ȃ����������Ă���B���p�e�͖��^���Z�t�ł���A���h���E�V���������������A�t�����X���𒆐S�ɟ��E�ȉ����c���Ă���B�X�y�C���̃C�X�p���H�b�N�X�́A�Z�p�������h������Ă����炵���A��₭�����F�Ȃ����捂ȉ��y��t�ł�B�t�ɕ�Vox�Ȃǂɂ́A���炩��EMI�n�̃N���[���g���Ę^���������̂����݂���B�e�n�̘^���N���[�͐V���ł����Γ��h���̂悤�Ȃ��̂ŁA�^���̊�悳������@�ށA�l�ނɗZ�ʂ𗘂����Ă����\��������B
�@�͂����ă��m��������EMI�̃r���[�h�̂悤�Ȕ��G��́A�ǂ����痈��̂ł��낤���B���ɖ؊ǂ̒���̉��₩���́A���̃��[�x���ł͓���A�I�[�P�X�g���ł̑Θb��L���ɂ��Ă���B���y�ł̏_�炩�����R�ȃC���g�l�[�V�����A�s�A�m�̉��ʂ̂Ȃ��ώ��ȋ����A���F�̃o�C�I�����̉��F�ȂǁA���_��������ƐF�X����B�����炱���A���̂ǂ��肵���u���̗ϓւ̋����v�ɂ͈�a�����o����̂ł���B�Ƃ���p���̘V�G���W�j�A�́ALP�̉��𗿗��ɗႦ�āuEMI�������ŁADecca�͒��ΏĂ��v�ƌ������Ƃ��B���ƂȂ��Ă͉��ɂ܂���Ĉꏏ�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɗp�S���Ȃ���Ȃ�܂��B �y�N���f���U�̉B���q�H�z �@�~���@�̏����Ƃ��]������N���f���U�B���̗D��ȉ��䂦�ɁA�N�����pHMV�̈�ۂƌ��т��邪�A���͂��ꂪ�傫�Ȋ��Ⴂ�ł���B���ꂱ�����A�����J���E�T�E���h�ɌN�Ղ���WE�Ђ��A1925�N�ɓd�C�^�������Ƌ��ɐ��E�ɑ���o�����h�q�ł���A�f�U�C���A�l�[�~���O���Ƀ��B�N�g���A��ɍʂ��Ă��邪�A���h�ȃA�����J���̒~���@�ł���B����ȑO�̒~���@�̎��g��������������̂��Ⴍ��オ�����J���������Ȃ̂ɑ��A�N���f���U�̂���͒�悩�璆����܂Ńt���b�g�ɍĐ��ł��鉹�������������Ă����B����͈�ʓI�ɍl�����Ă��郈�[���s�A���E�T�E���h�Ɠ����u���ł����āA�ނ���Â��p�O�����t�H���̉����J���������Œ�������Ă������Ƃɂ��C�t�������̂ł���B�ł�HMV�����̒~���@�͂Ƃ����ƁA�����J���������c���Ȃ���ቹ�̑�����}�����o�����X������Ă���A���҂̒�����������ܒ��I�ȃX�^�C���ł��������Ƃ�����B
�@����ŁA���������Ƀg�[�L�[�p�̃}�C�N�Ƃ��Ă悭�g��ꂽ�̂��A�h�C�c��Reisz�Ђ��J�������J�[�{���}�C�N�ŁA1930�N���BBC��Pathe�X�^�W�I�Ŏg�p���ꂽ�B�����͍���̎q�������Ăɘ^���悤�ɂł��Ă���A�ȉ��̌��w�^���ł����̗ǂ��͏\���ɏo�Ă���BHMV�̘^�����i�ł悭������WE���{�^���}�C�N�́A����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�t���b�g�l�X�ł��邱�Ƃɒ��ӂ������B
�@�����Ńu���e�B�b�V���E�T�E���h�ɂ݂�Q�̒����������Ă���B�܂�1900�N���瑱������̋����������D�ރO���[�v�ƁA1925�N�ȍ~�̊����̗ǂ��������D�ރO���[�v�ł���B���̃X�s�[�J�[�E���[�J�[�Ō����A�J���������̑�\��Lowther�ł���A�_�炩�����̑�\��Goodmann�ł���BTANNOY��QUAD�͂��̂ӂ��̒��ԂƂ������Ƃ��낾�낤�B�悭�C�M���X�̃I�[�f�B�I�͓T��ȃ��[���s�A���E�T�E���h�ƕ]����邱�Ƃ������̂����A���͂ƂĂ��o���G�e�B�[�ɕx��ł���̂ł���B������TANNOY���p�̃G���N���[�W���[���̂܂܂Ŏg�p���Ă����̂�Decca�̂ق��ŁAEMI�͋������^�C�g��Lockwwod�Ђ̃o�X���t�����g���Ă����B �@�d�C�^�������̉pHMV���A�N���f���U�𒆐S�Ƃ���WE�T�E���h�Əd�Ȃ�̂����A����̕�Victor�̂ق��͂ǂ����Ƃ����ƁA�Ⴆ�J�U���X�̃`�F��������ł͓����悤�ȃg�[���������Ă���B�傫���Ⴄ�̂̓I�[�P�X�g����i�̘^���ŁA��Victor�͒��ډ��𑽂��܂݃_�C�i�~�b�N�ȉ����u������̂ɑ��A�pHMV�̓z�[���̋������������_�炩�����Ŏ��^���Ă���B���̂悤�ȌX���́A1931�N��EMI�n�݂ɂ����āA�A�r�[���[�h�E�X�^�W�I�𗧂��グ��ۂɂ́A�����J�������Ă�WE47�^�R���f���T�[�}�C�N�Ƌ��ɁA�����炩��WE�X�^�C���̃_�C�i�~�b�N�Ș^���ɕϖe�𐋂���̂ł���B
�@���̈���ŁAWE���̃J�b�^�[�w�b�h�Ńv���X�������R�[�h�́A����v���X250�����܂�1���ɂ���1�̓������𐿋����ꂽ���߁A���ۓI�Ƀ��R�[�h�̔����Ă���EMI�ɂƂ��Ă͏d�������̂ƂȂ��Ă����B����ɉ����\�����@�ׂŌ̏����������WE47�^�}�C�N�́A��������Blumlein���m�ɂ��J�����ꂽ���[�r���O�R�C��������HB1�^�}�C�N�i�J���҂�Holman��Blumlein�̓��������Ƃ����Ƃ�����j�ւƏ��X�ɕς��A�����炭WE�Ƃ̌_��X�V��ł���1935�N�����肩��AHB1B�^�}�C�N�̐c�̋������ւƕς���Ă����B�����Blumlein���m�����Ƃ��ƉpColumbia�o�g�̃G���W�j�A�ł���A���Ƃ��ƃ^�C�g�ȉ����D�݂ł��������Ƃ��������Ǝv�����A�����ł�5kHz���{4dB�����グ�����ƂłƂĂ��D�܂����T�E���h�ƂȂ����Ƃ���A�s�A�m�̎��^�ɗD��Ă����炵���B�pHMV�╧Pathe�̗H���ȉ����D���Ȑl�ɂ́A���N�̃}�G�X�g���̍Ę^����������o�߂��悤�Ɋ����C�ɓ���Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ����낤���B������1936�N����J�n���ꂽBBC�̃e���r���^�iAlexandra Palace�j�ł͂悭�g��ꂽ�Ƃ�����݂�ƁA�o�͂̍������Ƃ���R�[�h�̈����������Ă��m�C�Y�ɋ����Ƃ������ʂƁA������̎����グ��Shure�Ђ̃{�[�J���}�C�N�Ɠ��l��Low-Fi�@��ł����ēx�̍������Ɗ����邩������Ȃ��B���ł͐M�����������A���̃��[�r���O�R�C�����}�C�N�͔��ɍ����ŁABBC�̃��{�����}�C�N����9�������̂ɑ���40�������Ƃ����B�l���Ă݂���{�����̓f���P�[�g�Ȃ���ޗ���͂��܂�|���炸�A���[�r���O�R�C���͐U���ƃR�C���A�G�b�W�T�X�y���V�����Ȃnj��\�ȑg�ݕt�����x���v�������B1930�N�̏����^HB1A�̓T�X�y���V�����̒��������܂��������ɃR�C�����C���Ă��܂��A�o�C�m�[�������^�̎����Ŏv�����悤�Ȑ��ʂ������Ȃ������Ɖ]����B���̃}�C�N��HB1E�܂Ńo�[�W�������d�ˁA1955�N���܂Ŏg��ꂽ�B
�@�������āAEMI�̃T�E���h�ɂ́A�@�pHMV-Pathe�̏_�炩���g�[���A�A��WE�̃L���̂���_�C�i�~�b�N�ȉ��A�BBlumlein���̘^���Z�p�̉��v�A�C���̃h�C�c�̃}�O�l�g�t�H���̋Z�p�A���X���������Ă���A���E��̃��R�[�h��ЂȂ�ł͂̕��G�ȍj�������������ƌ�����B������EMI�Ƃ�������ȃW�O�\�[�p�Y���̋���I���g�ݏグ���Ƃ��������܂�̂ł���B
�@���̂��Ƃ͉��������Ă��邩�ƌ����A�S��㇗��ɂ݂���p���I�[�f�B�I�@��̂قƂ�ǂ́A�ꕔ�̏㗬�K�����C�O�����̓��Y���ł���A�C�M���X�����̂����̊Ԃɓ͂����Ƃ͋H�ł������Ƃ������ƁB�����đ����̐l���d�~�iRadiogram�j�������ARIAA�ɂȂ������78rpm�Ղ��ɒ����Ă����̂ł���BQUAD�ł����A1967�N������33�^�v���A���v�i�g�����W�X�^�[���j��5kHz�̃n�C�J�b�g�t�B���^�[�����Ă������炢�ł���B�����������Ƃ�EMI�̃T�E���h�ɂ��āu���̌������̂悤�ȉ��v�ƌ���ތ����ƂȂ��Ă���Ǝv���B�C�M���X���̃I�[�f�B�I������p���v���X�̃��R�[�h���ō��̉��Ŗ炵�Ă���邾�낤�ƒN�����l���邪�A�����̃C�M���X�������������T�E���h�́ASP�^���̉������Ƃ��Ƃ��������D�܂ꂽ�Ƃ����悤�B����ł��p���v���X�����d�����̂́A����EMI�̖��̎�ɒĂ��Ă���̂ł���B �@���{�ł��̌���ɔ��Ԃ��|�����̂��ASP�����ՁiGR�V���[�Y�j�ł��낤�B���{�ł�1957�N���甭�����ꂽ��A�̕����V���[�Y�́ASP�Ղ̃X�N���b�`��������邽�߁A���͂ȍ���t�B���^�[���|���Ă���A���ꂪ�J�}�{�R�^�Ŗ������̂Ȃ����̌����Ƃ��Ȃ��Ă���B���ꂪ���炭SP�^���Ɖ]���Αш�̋����l�܂�Ȃ����Ƃ��������[�߂Ă����B�ŋ߂ɂȂ��āA�匳�̔Ō�����ăA�[�J�C�����J�����ꂽ���Ƃɂ��A�R���N�^�[�ɂ��ǎ��ȔՂ̕�����A�q�ɂɖ����Ă��������}�X�^�[�������肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ������߁A78rpm�Ղւ̕]�����啪�ς���Ă����Ǝv���̂��BCD����ɂȂ��Č��Ղɂ���X�N���b�`�m�C�Y�ɑ����e�ɂȂ������Ƃ��K�����Ă��邩������Ȃ��B
�@���m�������̃��}�X�^�[���A21���I�ɓ����Ă��Ȃ萮������Ă��Ă���A�����̃}�X�^�[�e�[�v���邱�Ƃ�A�����v���X�̔ՋN�����ȂǁA�l�X�Ȏ�@���g���ĕ�����ׂ���悤�ɂȂ����B���̂��Ƃ�EMI�̃T�E���h�݂̍���Ɍ��āA��l���o�ɏI�n���Ă����{�Ƃ̐��K�Ղ��q�ϓI�Ɍ��ł���@��^����ꂽ�Ǝv���B����EMI���}�X�^�[�e�[�v�̍Ē�����A�@�ނ̐����A���}�X�^�[�̕��@�Ȃǂɍ��͂𒍂��悤�ɂȂ����B�����������Ƃ��A�ႦCD�ł��N�I���e�B�̌��オ�}���A�݂肵����EMI�T�E���h���Ĕ�������@��ɂȂ����Ǝv���Ă���B �@��������EMI�̃T�E���h�ʂł̐����l�X�Ȋp�x���猟���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������߁A����܂ŋc�_�̗]�n�̂Ȃ����̂Ǝv���Ă������t�ւ̕]�����܂߂āA���Ȃ�V�N�ȕ��͋C�Ŏ~�߂邱�Ƃ��ł������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���߂āuEMI�̎���v�Ƃ������̂ɃN���[�Y���Ă����̂��ʔ������낤�B �y��Hi-Fi���z�ȁz �@������EMI�Ƃ������僌�[�x����������C�M���X�̃I�[�f�B�I�E�́A1930�N��ɂ���Ӗ��ُ�Ȕ��W�𐋂���B�Ƃ�������O�ɂ�����100�`8,000Hz�̕ǂ������Ȃ�˂������A�X�e���I�^�������s�����ȂǁA20�N��̋Z�p���R���V���}�[�s��ŗ��N���Ă���̂ł���B �@Lowther�̑O�g�ł���Paul Voigt�̃X�s�[�J�[�Ȃǂ͂��̍ł�����̂ŁA1933�N�ɊJ���������j�b�g�́A�T�u�R�[���A���݂�_���p�[�Ȃǐ�i�I�ȋ@�\�ڂ����t�������W�ŁADomestic Corner Horn�Ƃ����L�ш�z�[���ɑ��������B�ŏ��͓����������Ƃ��ăX�^�[�g����Voigt���̃X�s�[�J�[�́A���炩�Ƀn���h���C�h�̎���i�ŁA�܂��}���`�E�F�C�̎�����10kHz�Đ����c�_����Ă�������ɁA12kHz�܂ł̍L�ш�Đ����������Ă����i�����V���O��Iconic�ł���1937�N�ł���j�B����ɒǂ����K�i��1945�N��Decca ffrr�ł���A�܂��ɂԂ�������̔��z�ł������B
�@���������ɂ̓e�[�v�^���̑n�����ł�����A����1924�N�Ƀh�C�c�Ńe�[�v�^���@���J������Kurt Stille���m��Marconi�Ђƒ�g���A1932�N��BBC�Ɍ����X�`�[���e�[�v�^���@��[�i�����B���̓����̃X�y�b�N�͍Đ����g��100Hz�`6kHz�AS/N��35dB�Ƃ������̂ŁA32���̔ԑg���^��25�p�E���h�i��11kg�j�̃��[���������B1937�N�ɂ͎��C�w�b�h�����ǂ��A�ш��8kHz�ƐL��������SP�Ղ̃��x���܂Œǂ��������A��Presto�Ђ�1934�N�Ƀ����[�X�����A�Z�e�[�g�^���@�i���g��50Hz�`8kHz�AS/N��50dB�j�ɔ�ׁA�R�X�g�A���\�A�_�r���O�̎�y���Ȃǖ��炩�ɕ��������A1941�N�ɓ���������A20�N�ȏ���A�Z�e�[�g�^�����g���邱�ƂɂȂ�B���Ȃ݂Ɏ����e�[�v�̊J�����̓�BASF�Ђ�AEG�Ђ�Magnetphon���g���čŏ��Ƀe�[�v���^�����̂́A1936�N�̃h�C�c�ɉ��t���s���̃r�[�`�����^LPO�ł���B�s���ɂ������h�C�c�ɂ����āA�����̃C�M���X���s��̃^�[�Q�b�g�ł��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A���̌�1938�N�ɃI�����_�o�R��Philips-Miller���̎����e�[�v�^���@���[�i����邪�A1939�N����̃h�C�c�Ƃ̐푈�ŊW���r�₦�Ă��܂����B
�@����ŁAEMI�̘^���Z�t�ł���Alan Blumlein��1931�N�̓�������Ƀo�C�m�[�����^���\�����B����i�K�ł͌��w�t�B�����Ɂu�b���Ȃ��獶����E�ɕ����v�Ƃ������̂��������A�X�e���I�p�̃J�b�^�[�w�b�h���J������1934�N�ɂ́A�A�r�[���[�h�X�^�W�I�Ńr�[�`�����^LPO�i���[�c�@���g�̃W���s�^�[�����ȁj�̃e�X�g�^�������s���Ă���B���̂Ƃ��̃X�e���I�^�������͑o�w�����}�C�N��45�x�Ō�������������ŁA����������WE�w�c������p��3ch�����������̂ɑ��A�ƒ�p�ɓ���݂₷���V�X�e�����l�Ă������ƂɂȂ�A���2ch�X�e���I���_������t���邱�ƂƂȂ�BBlumlein��UL��H�̊J���҂ł�����A1942�N�܂ł̒Z�����U�̊Ԃɗ��j�Ɏc�鑽���̔����������B������EMI�ɂ��X�e���I�E���R�[�h�̔̔��͉�������A1950�N��܂œ�������邱�ƂƂȂ�B���Ȃ݂Ƀr�[�`�������́A1936�N��LPO�Ƃ̃h�C�c���t���s�̍ۂ�BASF�Ёi�����x�[�X�̎��C�e�[�v�̊J�����j�ɗ��������AEG�Ђ̃}�O�l�g�t�H���ł̃e�X�g�^���ɋ��͂�����A1937�N�Ƀ����h����HMV�V���b�v���Ď�������̊J�����ŃX�s�[�`��S��������ƁA���̎���̐�i�I�ȃI�[�f�B�I�ɂ��Ȃ�̋���������Ă����悤���B
�@���������l�X�Ȑ�i�Z�p��1930�N��̃C�M���X�̃I�[�f�B�I��Ȋ��������̂́A���p�܂ł͂قlj������̂���ł������B�ڂ̑O�̐푈�̊�@���A�������������u�����R���Z�p�֓]���𔗂����Ǝv����B �@�Ăѐ��E���C�M���X�̃I�[�f�B�I�ɒ��ڂ���̂͐��̂��Ƃł���B�����ȃg�s�b�N�X���L���邾���ł��ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B���Ȃ݂�EMI��LP������̂�1952�N����ŁA����ȑO��78rpm�Ղł̃����[�X�ƂȂ�A�����̃C�M���X�l��1960�N��O���܂�78rpm�Ղ��������Ă����B
�@���ꂾ�����h�����̃I�[�f�B�I�@�킪�A�ЂƂ̍��ŁA���������N��ɏo�����Ƃ����̂́A�܂������đ��ɖ������낤�B���悻���s�Ƃ������̂��ڂ݂��˂������Ă邾���ŁA����ɉ����Ɠd���i�Ƃ��Ă̓d�~�������̂ł��邩��A���m�������̉pEMI���͂ފ��͍�����[�߂����ŁA��`�I�ȓ����ȂǂȂ��B�����̃o���G�[�V�����͉pEMI�̑t�ł�T�E���h�ɑ�����A�^�ۗ��_�������ēW�J���Ă���悤�Ɏv����B����ł͋q�ϓI�ɂ��ꂾ�ƌ�������̂�����̂��H�@�����A���̃C�M���X�l�ł����N���v���t���Ȃ��������Ƃ��낤�B �yBBC�Ƃ̍���������z �@�Ƃ���łǂ����Ă��ꌾ�t�������ċN�������̂��ABBC��EMI�̊W�ł���B�����̐l��BBC���j�^�[��EMI�̘^������S���̂��ƐM���Ă���B�����������u�������C�������̃����|�C���g�}�C�N�ł̎��^�������̂́A���X1950�N��܂ŁB�X�e���ILP������O�ɁAEMI�͂Ƃ��Ƀm�C�}�����}�C�N���g�����}���`�^���Ɉڍs���Ă����B����ȑO�͂ǂ����Ƃ����ƁA�A�r�[���[�h�E�X�^�W�I��1931�N�ɗ����グ���ۂɂ́A�^���ɂ�WE���J����������� 47�^�R���f���T�[�}�C�N���g��ꂽ�B����ŁA��������BBC��GE�Ђ̃��j�^�[�X�s�[�J�[�A�pMarconi�Ђ̃��{���}�C�N�A��Presto�Ђ̃A�Z�e�[�g�^���@���g�p���Ă����B�܂�BBC��RCA�n����̋Z�p��g���Ă���AWE�n��EMI�Ƃ̓T�E���h�X�����S���قȂ�B���҂��߂Â����̂́A���m������������X�e���I�����Ɏ���킸��5�A6�N�Ƃ����̂����ۂł���B�����炭BBC��EMI����u�������C�������̃X�e���I�Z�p�̒��邽�߁A�o���̋Z�p�𗬂��s��ꂽ�Ǝv����B �@���m���������烂�j�^�[�ɍ̗p����TANNOY�ɂ��Ă��ABBC�͐��܂��Ȃ����Ɍ������������ŁAEMI��Decca�̌��ǂ���1951�N�ɓ��������Ƃ��Ƃ͏d�Ȃ��Ă��Ȃ��B���ɊJ�����ꂽ���^�X�s�[�J�[��Lorenz�Ђ̃c�C�[�^�[���g�����o�܂��ABBC��Parmeko��7kHz�܂ł̑ш悵���Ȃ����߁ALorenz���c�C�[�^�[��ܒ��I�ɑ������̂ɑ��AEMI�̓z�[���^�c�C�[�^�[�͍̗p����Lorenz�Ђ̌��̎d�l�P���Ă���B���Decca��Decola�X�e���I��EMI�̑ȉ~�t�������W���j�b�g���̗p�����B���̂悤�ɑǓI�Ɍ����Decca�Ƃ́A����TANNOY���X�s�[�J�[�����j�^�[�Ɏg���ȂǁA�n�[�h�E�F�A�̖ʂł͂��ٖ��ȊW�ɂ���B �@�܂�BBC�����܂��Ȃ��̃h�C�c���i���g�����e�[�v���^�ɔᔻ�I���������Ƃ������̋Z�p�������画���Ă���B�i�����Eckmiller�X�s�[�J�[�ɑ��Ă����l�ł���j�@����ɑ��AEMI�͓ƃG���N�g���[���̃X�^�b�t����}�O�l�g�t�H���̘^���Z�p�����������������A1949�N����C�M���X�����ł��e�[�v�^�����s�����B �@���̂悤�ɔ��R�ƋZ�p�W����v���Ă��Ă��A���Ԏ�����@�_�����ݍ����Ă��Ȃ��̂ł���B�A�����J�ɂ�DJ�Ƃ����E�Ƃ����邪�A�C�M���X�ł̓��R�[�h�ƊE�̌���������ǂ��N���Ȃ����߁A1960�N��܂Ń��R�[�h�Ŕ̔����Ă���y�Ȃ̕����ɐ������|�����Ă����B�����Č����AEMI��BBC�̋Z�p�w�́A���R�[�h�ƊE�ƕ����ƊE�A���c�ƍ��c�Ƃ����Ⴂ������A�����ɋ�����u���Ă����悤�v���B
�@�悭�u���e�B�b�V���E�T�E���h�̓����Ƃ��ăt���b�g�l�X���������邪�A�f���ȓ����ł���Α������ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���{���ɑ����t���b�g�ȓ����̃X�s�[�J�[�i�Ⴆ��BTS�K�i�̃��N�n���j�ł͂��܂�ǂ����ʂ������Ȃ��B���Ă̓��ŔՂɑ�������ӌ��Ǝ��Ă��āA�v���X���ɃC�R���C�W���O���Ȃ��f���ȓ������A�_�ɂȂ��āA������̉��C���p�N�g�̂Ȃ����Ɏd�オ���Ă��܂��̂��B����NHK�̘^���͍��̊�ł݂�Ɖ��ɕȂ̂Ȃ��ǎ��Ȃ��̂ŁA�I�[�f�B�I�I�ɂ͖ʔ����Ȃ����̂́A�ނ�������̏��I�������Ă��邩������Ȃ��B�������Ƃ�BBC�ɂ�������̂����AEMI�̃T�E���h�Ƃ͎�Ⴄ�悤�Ɏv���B �@�C�R���C�W���O���قƂ�ǂ����ɕ�������BBC���j�^�[�̓������݂�ƁA�E�[�n�[��800�`2,000Hz�̒������5dB���x�̃A�N�Z���g��^���Ă��邱�Ƃ�����B�t���b�g�l�X���|�Ƃ��Ȃ�����A�����Ƃ��Ă͂��h�߂Ɏd�グ�Ă���̂��B����ɍ��悪��l�����\�ꂪ���Ȃ��̂ł���B����͌Â��͉p�O�����t�H���̒~���@���瑱���`���I�Ȏ��g���o�����X���g���������ʂł���A����ɓƓ��̎�������������錍�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���BBBC���j�^�[�̓����̗��j��R�����ƁA1930�N����N�_�Ƃ����A�����J�̃I�[�f�B�I�Z�p�Ɍ��т��Ă����̂ł���B
�@�ȉ���BBC��Parmeko���̗p����ۂɔ�r��������TANNOY��EMI�̓��������A��L��BBC���j�^�[�̌n���Ƃ͈قȂ�A�����悪��l���������ł���B�Ⴂ��TANNOY�iDecca�j����������������グ��̂ɑ��AEMI�̍����d�~�͍��悪�Ȃ��炩�ɉ��~��������iBBC�̊��z�ł͈Â����j�ƂȂ��Ă���B���̂Ƃ�EMI��Kelly�����{���c�C�[�^�[���̗p���Ă����炵���A�p���[�����W�̕K�v�Ȃ��ƒ�p�V�X�e���ɍœK�����Ă������Ƃ�����BEMI��1931�N�̃A�r�[���[�h�E�X�^�W�I���ݎ��������E����ʂ��āA�Z�p�̕ێ琫�������ɂȂ�A�����˂������悤�Ƃ���Decca�Ƃ̃T�E���h�ʂ̘������������̂ł͂Ȃ����낤���B�C�M���X�l�̍����I�ȕ��̌��������炷��ƁA��蒉���x�������Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̂Ƃ���ŏ��̊�ƂȂ����Z�p����̐ςݏグ�ɍۂ��A�����I�Ȃ��̂����傫�������Ă���Ƃ�������B
�@���Ȃ݂�1948�N��BBC���|�[�gM008�ɏo�Ă���EMI���̃X�s�[�J�[�Ƃ́A�ȉ~���j�b�g2�{�ƃz�[���t���{���c�C�[�^�[�i�����炭Kelly���j���g�p���Ă���ƋL�ڂ���A1946�N��HMV���J������3000�^�d�~Electrogram De Luxe�ƌĂꂽ�@��ŁA�ŏ���Abbey Road�ł̂���I�ڎ��ɂ��Ă�Gramophone��1946�N9�����ɋL�����ڂ��Ă���BQUAD���ŏ��ɊJ�������R�[�i�[���{���Ƃ����X�s�[�J�[�ƍ\�������Ă���A30Hz�`15kHz�܂ł̍Đ������W���ւ����B1948�N�����̉��i�Ł�395�Ƃ���A���b�O�����ō��̍Đ��@��̊J�����w�������Ƃ�����̂́A�����炭���̋@��ł������Ǝv����B����3000�^��EMI�̋Z�p�͂��֎����邽�߂ɁA�R�X�g�x�O���Őv���ꂽ�������A���ɑ䐔�����Ȃ������Ǝv���A����I�ڎ��̌��1948�N��Ernest Fisk���ɂ�蔃������A�I�[�X�g�����A�Ń��R�[�h�R���T�[�g�ȂǂɎg��ꂽ�B�ŏ��̃L�����x���ł̃R���T�[�g�́A�V���i�[�x���ƃt�B���n�[���j�A�ǂɂ��x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�S�Ԃ��Đ����ꂽ�Ɖ]���A���̎����̘^���A���p�b�e�B��k���[�Ȃ�1940�N��ɚ�܂������y�Ƃ��D�ސl�����ɂ́A�ЂƂ̕��������������ƂɂȂ邾�낤�B����3000�^Electrogram De Luxe��1952�N��Sydney Morning Herald���Œ��Ô̔��̍L���i��60�j���o���ꂽ�̂��Ō�ɁA���j�ォ��p�������Ă��茶�̍����d�~�Ƃ�����B �@���ۂ̂Ƃ���AEMI�ł�Lorenz���c�C�[�^�[�̎g�p�́AKelly�����{���c�C�[�^�[�̃R�X�g��ێ�̊W����Ë������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A1949�N��HMV Radiogram 1609�i���i�F��103�j���瓋�ڂ��ꂽ�B���̎����ɂȂ��EMI�̓h�C�c�E�G���N�g���[������e�[�v�^���Z�p���z�����A���ЂɃe�[�v�^���@�i�pBTH�А��j��u���悤�ɂȂ��Ă����B�J�������͐풆����}�O�l�g�t�H���ƃm�C�}�����}�C�N�AEckmiller���j�^�[�X�s�[�J�[�Ƃ����g�ݍ��킹�ŁA�o�C�m�[�����^���̎����ɎQ�����Ă������߁A���������Z�p�ɏK�n���Ă������A���b�O�����D�ꂽ�^���Z�p�ɑ������璍�ڂ��Ă����Ǝv����B �@EMI��92390�^�ȉ~�t�������W�X�s�[�J�[�́A1960�N��̃X�e���I�p�X�s�[�J�[�Ƃ��ėL�������A1940�N��̃X�^�W�I�ʐ^����݂Ă����Ƒ��������ɊJ������Ă���A1937�N�̍����d�~Autoradiogram 801�łقړ��l�̃��j�b�g�i���̎��_�ł͗㎥�^�j�����ڂ���Ă����B�������������d�~�̓M�j�[���݂ł̉��i�\���ł��邱�Ƃ���A�M��������ɏ�����x�T�w�̎������Ƃ����l���̋������Ƃ�����BEMI���u�������C�����m��擪�ɋZ�p�v�V��簐i���Ă��������̏��Y�ł��苻���[�����A����ȑO�ɂ�1934�N��Marconi�Ђ������d�~Marconiphone 292�œ��l�̃��j�b�g�����ڂ���Ă������߁A�{����Marconi�Ђ������d�~�ł̎g�p��ړI�ɊJ�����ꂽ���j�b�g���AEMI�����j�^�[�Ɏg�p�����Ƃ����̂����ۂ��낤�B���̌��HMV�u�����h�̓d�~�ɂ͂��̃X�s�[�J�[���悭�g���Ă���A�v���t�F�b�V���i���Ȍ���ł���Ȃ���z�[�����[�X�̂��߂̋Z�p�J���Ƃ������ʂ��������Ƃ�����B1944�N��BBC��M004���|�[�g�ł��̑ȉ~�X�s�[�J�[��P�̂ő��肵�����ʂł́A4.5kHz�Ƀs�[�N�������������C�h�����W�E�X�s�[�J�[�ł��������Ƃ�����B���̂Ƃ���BBC�̕]���́AEMI�̃��j�b�g�͍����Ƀs�[�N������ƈ�R���Ă���AGEC�����j�b�g��2.5kHz�Ƀs�[�N���������Əs�ʂ��Ă���B����ŁA�ȉ~�X�s�[�J�[�Ƀ��{���c�C�[�^�[��t���������d�~Electrogram�ɂ́u�Â����v�Ƃ����]���Ȃ̂ŁA���邢��BBC�̋Z�p�҂�EMI��ь������Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �@����������Decca�̍����d�~Decola�́A�ŏ���Goodmann�Ђ̃t�������W�{�_�u���E�[�n�[�A1949�N�ɂ�TANNOY�Ђ�12"����2way�{�_�u���E�[�n�[�ɂȂ��Ă���B�����炭�����́A�A�����J�ł�LP�����ɍ��킹�Đ��삳��Ă���A�C�M���X�̉ƒ�ɂ͂قƂ�Ǔ͂��Ȃ��������낤�Ǝv����B
�@BBC�̑傫�Ȍ��т́A�N���V�b�N���y��ǎ��ȃX�e���I�����ő��葱�������ƂŁA�u�������C�������̃����|�C���g�E�}�C�N�ɂ��^���́A�X�e���I�V�X�e���̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W�̕W�����Ɍq�������B��Ƀu���e�B�b�V���E���b�N�̗D�ꂽ�~�L�V���O���A�������������I�w�i���琶�܂ꂽ�Ƃ����悤�B�܂�C�M���X�ŃX�e���I�^���̃m�E�n�E���n������܂łɂ́A�����ŕ����鍑�c�����̏��͂��K�v�������Ƃ�����B���Ȃ݂ɂ��̃u�������C��������1930�N���EMI�ŊJ�����ꂽ���̂ŁA�����̊W���܂ߎ��R�Ɏg����悤�ɂȂ�܂ł̊Ԃ��ABBC��EMI�̖����ł������Ǝv����B �@���̈Ӗ��ł́ABBC��EMI�̗ǂ��p���҂̂悤�Ɏv���邪�A�ŋ߂ɂȂ���BBC���^���������ւ���A�s��ɏo�Ă���悤�ɂȂ��ĉ��߂Ĕ������̂́AEMI�̘^����BBC�̂���Ƃ́A�g�F�n�ł͋��ʂ��Ă��邪�A�T�E���h�X�e�[�W�̑��肪�傫���قȂ�BBBC���j�^�[�Ƃ���LS5/1�������[�X���ꂽ1960�N���ɂ́ABBC�̓X�e���I���^�̕��@���܂ߊ������[�J�[���痣��ēƎ��K�i����ݎn�߂Ă���A�]�����獂��͍L���g�U���ꂽ�ق����ǂ��X�s�[�J�[�Ƃ����펯���痣��āA�`�����l���Z�p���[�V�������d�������v�ւƈڍs���Ă���B���������r���Č�����̂́ABBC�����c���������Ȃ��玩�R�ȉ�������̂܂��^���Ă���̂ɑ��AEMI��1960�N��̃X�e���I���ɃA�����J�s����ӎ������������A�}���`�}�C�N�ɂ��l�H�I�ȃo�����X���ڗ��B
�@1960�N���ʂ��ABBC���C�M���X�̉ƒ�ɑf���ȃX�e���I�𑗂葱�������ʁALP�̉�������l�������̂ɕω����Ă������\�����ے�ł��Ȃ��B1950�N��̃v���X��1970�N��̂���Ƃ̈Ⴂ�́A�J�b�e�B���O�}�V�[���̈Ⴂ�����邱�ƂȂ���A�D�܂����Ǝv����T�E���h�̕ω����傫���悤�Ɏv���B �@�����܂ł���ƁA���m�������A�X�e���I���̗����ɂ����āAEMI��BBC���قȂ�X�^�C���������Ă������Ƃ�����B�������Ȃ���A1970�N��ȍ~�͂��̕��s���͉������ꂽ�̂͌����܂ł��Ȃ��B���{�̃I�[�f�B�I����ʉƒ�ɍ��t�����̂�1970�N��ł��邩��A���҂����т��邱�Ƃɑ傫�Ȗ����͂Ȃ����A1930�N�ォ��1960�N��ɂ����Ă͖��炩�Ɍ��т��Ȃ��BEMI��BBC�͂��̊Ԃ̈����S�V�b�v�L���ɂ��ꂽ�ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ��B
�y�����₢�����z �@�����ʼnpEMI�̑��Ղ�H��ƁA����̓�肪�̂�������B1925�N�̓d�C�^������1952�N��LP�����܂łɁA���Ȃ��Ƃ���O�łR�A���łQ�̃W�F�l���[�V�����E�M���b�v�����݂��A���̂ǂ�����X�e���I���ɓ܂��̂悤�ȃT�E���h�|���V�[�ňꊇ��ɂ��ꂽ�Ƃ����ߋ�������B
�@����������肩�牽�����܂�邩�Ƃ����ƁA���E��̃��R�[�h��ЂƂ��đ��ʂȃA�[�`�X�g��i���Ă���ɂ��ւ�炸�A���t�̂��{���̃T�E���h���A���������N�������œh��ׂ���Ă���悤�Ȉ�ۂ��@���Ȃ��̂ł���B���B�N�g���A���̉�ƃ^�[�i�[�̂悤�ȉ敗�Ƃ��������̂��낤���B��������Decca�ɂ������āA�{���������������E�B�[���t�B���Ȃǂ͂��̑�\��ł��邵�A�ǂ̘^�����X�^�C���E�F�C�݂����ɕ�������Ƃ����͈̂Öق̗����ł��낤�B������̓t�����X�̐V�ÓT�h��ƃ_�r�b�h�̂悤�Ȋ����B�t�ɃR���g�[���^���Ŏg�����s�A�m�̂قƂ�ǂ��X�^�C���E�F�C�ł���ɂ��ւ�炸�A�v���C�G���̂悤�ɕ�������Ƃ����̂�EMI�B��͂肱�̉ۑ�����z����T���V���O�G���X���K�v�Ȃ̂��B���������Ђ̍����d�~�́A�X�s�[�J�[���j�b�g�������ʂ��Ă��邱�Ƃ���������A��������T�E���h�̈Ⴂ��������邱�Ƃ͓���B
�@����A�pEMI�ɂ��ăA���R���������|���ɂȂ����̂́A�A�����J���E�T�E���h�̈ꗃ��S���G���{�C�Œ�����EMI�̘^�������Ƃ̂ق��Y�킾�����A�Ƃ����P���ȗ��R�������B���ƌ�������ڍ���Ȃ̂ł���B�ڂ̋l�I�[�N�ނ�����ăr���[�h�̂悤�Ȍ���ɕ�܂ꂽ�֎q�ɍ��炳�ꂽ�悤�ȃ��b�`�ȋC���B�����������͋C�͑��̃��[�x���ł͖��킦�Ȃ����A���̉��𒆐S�Ƀg�[�������Ă����ƁA���̂قƂ�ǂ̃\�[�X�����������������ɂȂ�B��������O����X�^���_�[�h�Ƃ��ČN�Ղ��Ă������Ƃ����͂���B �@�l�I�Ȋ��z�����A���m�������̉pEMI�̍Đ��ɂ��ẮA�A�����J���i�ł̍Đ��Ƃ����̂��ЂƂ̗ǎ����Ǝv���B�Ƃ����̂́A�@1950�N��̉p�����̃r���e�[�W�@��ŗǎ��Ȃ��̂����Ȃ��A�������i�����c�����Ȃ��C��������Ȃ��ƁB�A�A�r�[���[�h�Ƀ��j�^�[�Ƃ��ē������ꂽTANNOY�ɂ��Ă��ADecca�̂悤�ɖ����p�����̂܂܃X�^�W�I�ɓ��������̂Ƃ͎���قȂ邵�A���҂̃T�E���h�̈Ⴂ��������������B�B�ŏI�I�ɂ͐���EMI�̍ł��傫�Ȃ����ӗl�̓A�����J�s��ł���A�A�����J�̃I�[�f�B�I�@��ɃL���b�`�A�b�v����悤�ɋZ�p���ǂ��d�˂Ă��邱�ƁA�Ȃǂ��������悤�B �@�������W�����u���̐S�ӋC�������L�[�ɗ����ł���̂��H�@���������^��͏�X�������B�������{�S�͗����ł��Ȃ��Ƃ��A���₩�ɃR�~���j�P�[�V�������炢�͂ł��邾�낤�B���̌��ʂ�����ł���B
�@EMI�ɂ��Ă������ƓK���ȃC�M���X�̃X�s�[�J�[���[�J�[�����������낤���A�������̉p���I�[�f�B�I�@��̗A�����Ђ́A�@TANNOY���X�s�[�J�[�{QUAD���A���v�{��Weathers���s�b�N�A�b�v�A�AGarrard���I�[�g�`�F���W���[�{LEAK���A���v�{Wharfedale���X�s�[�J�[�A���X�̑g�ݍ��킹��W�����Ă����Ƃ����ƂȂ̂ŁA���ݒm���鉩���̑g�ݍ��킹���������炠�������Ƃ�����B�������G���{�C�̃u�[�X�́A�P�Ȃ�w���Ҍ�����Hi-Fi�Z�p�̒�ł͂Ȃ��AWQXR�ǂ̃X�e���I�����iAM�AFM�g�̓��������j�̃X�s�[�J�[�����f���Ƌ��ɁA�ߖ����Z�p�Ƃ���EMI�̃~���[�W�b�N�e�[�v�̔��̏Љ�����Ă������ƂɂȂ�B���̌�EMI��1955�N�ɃX�e���I�e�[�v�̔̔��ɓ��ݐ邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����̕ăI�[�f�B�I�������ڂ������̃I�[�f�B�I�E�t�F�A���A��背�R�[�h��Ђ����ׂ����Ɏ艞����^�����\�����ے�ł��Ȃ��B �@EMI�̘^���̒��j�́A��͂�LP������1952����X�e���I���^�̎n�܂�1955�N���ɏW�����邪�A���}�X�^�[�Ղ���������t�����F���̂��Ƃ͂��Ă����āA�Ӌ��̃��p�[�g���[�ɂ������킢�[�����̂�����B���ꂪEMI�̂����[���Ƃ���Ȃ̂��B��O�̓d�C�^���ł́A�{�^���}�C�N��HMV����A1931�N�����EMI�iWE47�^�}�C�N�g�p�j�ł͂�͂艹�͈قȂ�A1935�N���玩�А�HB1B�^�}�C�N���g���T�E���h������ɕς��B���̐�O�̂R�����ꏏ�ɘ_����ƁAEMI�T�E���h�ւ̃A�v���[�`�͍����Ɋׂ�B
�@�y�[�W�ŏ��� |
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
