

���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R�j
�@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�����ł́A�T�u�V�X�e�������m���������W�I�����p�ɍ\�z������ɁA�[�˂̋@�ނ�Ђ��[�����������o���ẮA�ߋ��̂�����݂ƕ����������ʁA���X�̑�����ԂƂȂ����I�[�f�B�I�̌������Y�^����ɒԂ��Ă��܂��B�B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�Ȃ���JBL+Altec��PA�p�X�s�[�J�[�����m�����őg��ʼnx�ɂ͓����Ă܂��B 5)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |
||||||||||||||
�풆�E���h�C�c�����^��
|
||||||||||||||
�y�풆�E���h�C�c�����^���z �@�f�W�^���S���̎���ɂ����āA�����ł͂�����1930�`1960�N��Ƀ��m�����Ŏ��^���ꂽ�h�C�c�ł̕����^���\�[�X�������B�Ƃ����Ă������̍Đ���AM�����ƂȂ�B �@�������g��LP������1980�N��ɁA���̎�̘^���ɔ��Ă����荇���ł���B�u�Â��^���̂��߃m�C�Y���������Ă���܂��v�Ȃǂ̕��傪������āA�}�X�^�[���g���������̃_�r���O�E�e�[�v���Ƃ͋^���������A�Â����������}�j�A�ɓO���Ă����B�������Ńs���A�E�I�[�f�B�I�ɖڊo�߂��̂��A�A�E����10�N���炢�o���Ă���Ƃ����n���ł���B���̐t�̂�����݂ɁA�悤�₭������t����Ƃ�������Ă��悤�Ƃ́A�ŋ߂܂ŗ\�z���Ă��Ȃ������B�Ƃ������A�X�e���I�Đ����ꏄ�����Ƃ���ŁA�悤�₭���m�����ɊJ�Ⴕ���Ƃ��낾�B �@�O���܂ł́A�A�����J��Hi-Fi�̗��j�ɐ荞��ł������A�����ЂƂ̃~�b�V���O�����O���h�C�c�̃e�[�v�^���̗��j�ł���B�������̎���̘^���̓i�`�X�E�h�C�c�Ƃ����É_�ɕ����Ă��āA���̃S�^�S�^�Ńe�[�v�����U���Ă��܂��ȂǁA�Ȃ��Ȃ��𗝉����邱�Ƃ�����B�������̃h�C�c�̕����^���Z�p�́A�m���ɐ풆�̉�����ɂ���A�Đ��Z�p���l����̂͗L�v�Ȃ͂��ł���B�Ƃ����������Ēʂ�Ȃ��A�[�J�C�u�Ȃ̂ł���B �@�p�Ă���y���y�̔��W�������������̂ƈႢ�A�h�C�c���ŋL�^�Ƃ��Ďc���Ă�̂̓N���V�b�N���قƂ�ǁB���R�͖����ŁA�i�`�X����ɃW���Y�⌻�㉹�y�͑ޔp���y�Ƃ��Ĕr�����ꂽ���炾�B����ŁA���̎���̃N���V�b�N�^���̖��͂Ƃ��āA�h�C�c�̐l�X���������̂Ƃ��Ă�������ɁA�قƂ�ǂ̉��y�Ƃ��g������ттăq���[�}�j�b�N�ȉ��t�������Ȃ��Ă������Ƃɐs����悤�Ɏv���B�ł����̂��Ă����̂́A18���I����ɂ₩�ɍL�����Ă����h�C�c�n�����ڏZ�҂ŁA1600���l�K�͂̃h�C�c�n�Z�������Ƀh�C�c�����ɋ����ڏZ��������Ƃ������ԂƂȂ�A�u�̍��v�̎��Y��v�����ꖳ�ꕶ�ɂȂ��������̐l�X���ǂ��{�����́A��㏈���̓��ƂȂ��Ă����B�����č����������W�I��ʂ��ăh�C�c�l�̑������J���x���鉹�y�v���O����������̂ł���B���t�Z�p���ǂ��Ƃ������͂�����̂́A�h�C�c�I�ł��邱�Ƃ���ƈ�������邱�ƂƎ���d���������t�Ƃ������A��|�ɖ����|���Ă�������̉��t�͖��炩�ɐ����͂��Ⴄ�B �y�h�C�c�����K�i������@��ށz
�@���������@��ނɈ͂܂ꂽ�̐S�̃h�C�c�����^���́A�t���b�g�ȓ����̃X�s�[�J�[�Œ����ƁA�꒮���Ĕ���J�}�{�R�����ŁA���t�̖��͂Ɣ���Ⴕ�ĉ��̕n�����͔ۂ߂Ȃ��B�}�X�^�[�E�e�[�v�̍�����������A������ɃC�R���C�U�[�ŏC������ƈʑ��c�݂��ڗ����U���U���������ɂȂ�B���̓_�Ɋւ��Ă̓f�W�^���������i�����āA�����̃r���e�[�W�@��̃��X�g�A�Z�p�≹�̏C���Z�p�̌���ȂǂŁAAM������FM�������݂ɕ������邭�炢�̉������オ�݂���B����ŁA�n���ǂɔz�����ꂽ���̂̂Ȃ��ɂ́A�A�Z�e�[�g�ՂɃ_�r���O���ꂽ���̂����܂݂���B�A�Z�e�[�g�Ղ̓X�N���b�`�E�m�C�Y����邪�A�����̂Ƃ��ɍ����𗎂Ƃ������̂��قƂ�ǂł���B�A�Z�e�[�g�Ղł����^�������Ⴂ�Ƃ��ɁA�^�����ő��������ۂɃT�[���m�C�Y�����̂̓R���f���T�[�E�}�C�N�̎��^���Ƃ������Ƃ̏ƍ��ŁA���C�u�^���̏ꍇ�A�ߓ��͎��Ƀ}�C�N���ł̘c�݂��U�������ꍇ������B �@����̂������Ƃ����R����̓����̓R���f���T�[�E�}�C�N�ł̎��^�ɂ�钮����̃J�[�u�Ɏ��Ă���A�ނ��떯���p�̃��W�I�ɍ��킹�������}���Ď��^����p�^�[���������Ă����悤���B����͏����f�b�J�̂悤�ɒ���������������^���ł͋t��ɂȂ��Ă��܂��B �@���̂悤�Ș^���ƃX�s�[�J�[�̕Ȃ𑊌ݕ⊮����Ƃ������@���\�Ȃ̂́A�h�C�c�ł͐펞���ɓd�q���i�̋K�i�������Ȃ茰���ɐi�߂��āA�X�s�[�J�[���������C�o����Ђő��݂�OEM�������������������Ă��邽�߂��B���̐▭�ȑg�������A�ʏ�̃t���b�g�ȃX�s�[�J�[�ł̓J�}�{�R�^�����̘^���ɕ������闝�R�Ƃ�������B �yPA�ƊE�̎h�q������������z �@�Ƃ���ŁA����Ɩ{��Ȃ̂����A�A�����J�����G�ŕ`�����悤��EV�Ђ�SP8B�̓������݂āA�C�ɂȂ��Ă������Ƃ�����B����͗��2�`8kHz�܂ő����g�T�J�ŁA������h�C�c�n�X�s�[�J�[�̃g�[���Ƌ߂��̂ł́A���ɂB1970�N��܂ł̃h�C�c�̃I�[�f�B�I�́A�����ꕔ�̋Ɩ��p�������āA�W���[�}���E�T�E���h�ƌĂ�鋭�͂Ȓ�������D�ތX�����������B���̗��j�͐[���A�d�C�^���̎n�܂���1920�N�ォ�瑱���R��������̂ŁA�t�ɂ����Ζ��ĂŃJ�b�`���������̐��̂́A���̃g�T�J�̂悤�ɂ��Ԃ��Ă��钆����̋����ɂ���B�����X���̃T�E���h�ɂ́A�m�C�Y�����p�ɒ���������߂�Beyerdynamics�Ђ�DT48�^�w�b�h�z��������A�������1937�N���烂�j�^�[�p�Ɏg���ANagra�Ђ̃e�[�v���R�[�_�[�̃f�t�H���g�@�Ƃ��Ă����炭�g���Ă����B �@����ŁAEV�Ђ͑n��������{�Ƃ�PA�@��ł���A���Ăȉ����̂��߂̍œK�ȃC�R���C�W���O�ɂ��ēƎ��̌����������Ă����B1950�N��܂ł̓x���������������������E�h�l�X�E�J�[�u��y��Ƃ��ăX�s�[�J�[���J������Ă���AJensen�AAltec�AJBL�Ȃǂ̃t�������W�͂ǂ��2.5kHz�Ƀs�[�N���������ł������B�����1950�N���Hi-Fi�p�X�s�[�J�[���肪����EV�Ђ́A�J�^���O�ɓƎ��̉������_��W�J���ARegency II �̃J�^���O�ł͕����^���̃e�N�j�b�N��3�`6kHz�ȏ�������グ�邱�Ƃ��Љ�Ă���B���͂��ꂱ�����A�e�[�v�^���Ƌ��ɂɃh�C�c����A�����ꂽ���������Ȃ̂��B
�@�h�C�c�����Ǘp�̃}�C�N�A�e�[�v���R�[�_�[�A���j�^�[�́A�����̈ꋉ�i�𑵂��Ă��邽�߁A������������Ƃ������������B�����LP�ڍs���ɂ́A�����Ǘp�̃��R�[�h�v���[���[�͗ʎY���Ԃɍ��킸�A�t�����X��PIERRE CLEMENT�Ђɐ����ϑ����Ă���������������BEMT�Ђ��������n�߂�ȑO�̉ߓx�I�Ȏ���ł��邪�A������EMT�Ђ̃v���[���[�̂قƂ�ǂ�1966�N��Thorens�Ђ�������̂��̂ł��낤�B���̍����̂Ȃ���LP������ɐV���ɃI�[�f�B�I�@����w���ł���h�C�c�l�̐��͏��Ȃ��A�f�ʋ@�Ŏg���Ȉ�PA�ł̃��R�[�h�ӏ܉�悭�s��ꂽ�B���̏ꍇ�̓t�������W�Q�����g�����N�P�[�X�Ɏ��߂����̂��嗬�ŁAEL84�Ȃǂ��g�p����10W�ȉ��̏��^�A���v�ŋ쓮���Ă����B70�N��ȍ~��100W���̃I�[�f�B�I�Ɋ��ꂽ���݂ɂ����āA���̍������̗ǂ��͂��܂藝�����ɂ������̂Ǝv���B100W��K�v�Ƃ����̂́ABlatthaller�̂悤�ȑ�^���ʃX�s�[�J�[�����O�W���Ŏg���ꍇ�݂̂ł���B �@�ȉ��̐}�ł́A�ƒ�p�̔��e�Ɏ��܂�̂�3W�܂łł���A����ȏ��PA�p�Ƃ����敪�ɂȂ�B10W���x�̃A���v�ł��A���W�J�Z���Ƃ��Ȃǂ��Ă͂����Ȃ��B100dB/W/m�̔\�����ւ����t�������W�́A1W���x�ł����ʂ̉Ƃł͂��邳�����炢�ɖ苿���B 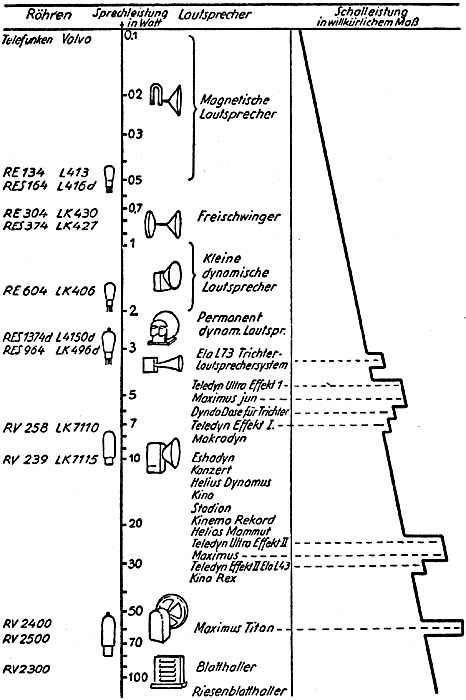 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1934�N�̃h�C�c���X�s�[�J�[�o�͕ʂ̈ꗗ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̑_����1�`2W�̏��^�i�v���X�s�[�J�[�j �@�����ASP8B�̋��͂Ȓ����悪���̂܂܃h�o�b�ƈ��Ă����̂��낤�B�C�R���C�U�[�ŕ����ƁA2.5kHz��10kHz��-6dB���Ƃ��Ă���ƕ��ʂ̃o�����X�ɂȂ����B����ł����͑���UTC C2080�Ōł߂āA������ۂ߂Ă���̂ŁA���ʂ̃t���b�g�ȃX�s�[�J�[���Ƃǂ��Ȃ�̂��ƁA�w�b�h�z�����q���Ŋm�F�B�B�B�Ȃ�Ƃ��ÏL��SP�^���̂悤�ȉ��B����ʂɒ�������SP8B�̃��j�[�N�����g�ɐ��݂��Ƌ��ɁA���C�Ȃ��q���ł���45�V���O���A���v�Ƃ̂���ǂ��o�����X�ɂ��������B �@�����Ŏ����I�Ƀw�b�h�z���o�͂�UTC C2080��83204�ɂȂ��ւ��Ă݂��Ƃ���A�ш�͋����Ȃ������A�A�����J���ȏL���̃v���v�����鉟���o���̋������ɕϖe�����B���������ꂪ�܂��ǂ������Ȃ̂ł���B�Â��W���Y�͂Ƃ������A�N���V�b�N���}�g�◬�ꂪ���m�ɂȂ�A�ӊO�ɑ������ǂ��BEL84�̂����₩���ƁAUTC�̃g�����X���z�h���b�v�̂悤�Ȏ����Ƃ��I���d�Ȃ荇���A�[������̃R�[�q�[�𖡂키�悤�ȉ��Ɏd�オ�����B�ŋ߂̃A���v�ō����Ǝv������A�r���e�[�W�E�g�����X�̋t�q�������肩�Ǝv��������B���ړd���𗬂��Ȃ��̂ŁA�ӊO�ɏ������g�����X�ł����Ȃ��g���邱�Ƃ��������B �@���̃g�T�J�ɗ���ŁA�O����Đ��ɋꗶ���Ă����̂��A�E�B�[���n�̕����^���𑽐��ۗL���Ă����Preiser���[�x���ŁA���ꂪ�܂��Ȃ̂��鉹���Œ����t���قǂ̃J�}�{�R�����B1950�N��̃E�B�[���̘^���Ƃ����A�����̐l��Decca��Westminster�ȂǁA�ǎ��ȃX�^�W�I�^���ŃV�X�e���̉��������킹�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B������Preiser���[�x���̘^���͂�����Ƃ����X�^�W�I�E�Z�b�V�����ł���B���ꂪ��������̘^���@�ނŘ^��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��قǁA�e�C�X�g���Ⴄ�̂ł���B����A���߂�EL84�{SP8B�Ƃ����g�ݍ��킹�Œ����Ă݂�ƁA�Y�o�����ꂪ�吳���B�l���Ă݂�A����Siemens�Ђ����������ȈՉf��ق�PA���u���݂Ă��A�t�������W�Ɏ����G���N���[�W���[�AEL84�ɂ�������ȃg�����X�B���͂����OK�Ȃ̂ł���B  �@�܂��̓E�B�[���E�R���`�F���g�n�E�X�l�d�t�c�ɂ��n�C�h���l�d�t�ȏW�B���̘^����1950�N���ORF�Ń����h�����m�̊ďC�̂��Ƃk�o20���ȏ�i�O�b�c����12���j�ɑ�ʂɘ^�����ꂽ���̂ŁA�����̊�V�Ȃ̊܂܂�Ă���_�ł��M�d�Ȃ��̂ł���B����ɉ����A�����ȃE�B�[���E�t�B���Ƃ�����ꂽ�A�E�B�[���E�R���`�F���g�n�E�X�l�d�t�c�̊Ô��ł���Ȃ���E�l�I�Ȍ|�������킦�邽�߁A��d�ɋM�d�Ȃ̂ł���B��������̃J�}�{�R�ł��邽�߁A�������^���ȏォ�甲���o�Ȃ��B���ꂪ�����ɕ��������B�ǂ��m����Westminster�^�����C�����̓������A�E�F�C�̉��t���Ƃ���APreiser�^���͋C�S�̒m�ꂽ���ԓ��Œ������������������B���ꂪ���͌ÓT�h�̃n�E�X���W�[�N���̂ɔ��Ƀ}�b�`���Ă���B����ł���EL84�͒ቹ�ɓK�x�Ȍy�������邽�߁A�`�F���̃X�b�Ƌ|�Ă邾���̃{�E�C���O�������Ɋy���߂�B �@�܂��̓E�B�[���E�R���`�F���g�n�E�X�l�d�t�c�ɂ��n�C�h���l�d�t�ȏW�B���̘^����1950�N���ORF�Ń����h�����m�̊ďC�̂��Ƃk�o20���ȏ�i�O�b�c����12���j�ɑ�ʂɘ^�����ꂽ���̂ŁA�����̊�V�Ȃ̊܂܂�Ă���_�ł��M�d�Ȃ��̂ł���B����ɉ����A�����ȃE�B�[���E�t�B���Ƃ�����ꂽ�A�E�B�[���E�R���`�F���g�n�E�X�l�d�t�c�̊Ô��ł���Ȃ���E�l�I�Ȍ|�������킦�邽�߁A��d�ɋM�d�Ȃ̂ł���B��������̃J�}�{�R�ł��邽�߁A�������^���ȏォ�甲���o�Ȃ��B���ꂪ�����ɕ��������B�ǂ��m����Westminster�^�����C�����̓������A�E�F�C�̉��t���Ƃ���APreiser�^���͋C�S�̒m�ꂽ���ԓ��Œ������������������B���ꂪ���͌ÓT�h�̃n�E�X���W�[�N���̂ɔ��Ƀ}�b�`���Ă���B����ł���EL84�͒ቹ�ɓK�x�Ȍy�������邽�߁A�`�F���̃X�b�Ƌ|�Ă邾���̃{�E�C���O�������Ɋy���߂�B �@�����āAR.�V���g���E�X�̕Ď��L�O���t��i1944�N�j�B�m�C�}�����R���f���T�[�}�C�N�AAKG���}�O�l�g�t�H���A�E�B�[���E�t�B���A���W�[�N�t�F���C���E�U�[���Ƃ��������̑g�ݍ��킹�Ŏ��^���ꂽ���Ƃ����e�[�v�^���ł���B�\�A�����Ɏ����čs���Ă��܂������߃I���W�i���e�[�v�͍s���s���B���ꂪ�u���R�Ɂv���h�C�c�̕����ǂ���_�r���O�e�[�v��������A���Ƃ����̉A������悤�ȃ��m�B���W�[�N�t�F���C���œ��X�Ɩ炵���nj��y��i�́A�����ł����c���������{�P�����Ȃ̂ɁA��̂������肵�����B�܂̍C�ł�������Ƃł���������̏��i�Ə�X�v���Ă����B�Ƃ��낪����������Ƒh�����B�h���t�@���`����ff���Y��ȃE�B�[���E�t�B���̂��́B�c�@���c�X�g�����A�ނ���㔼�̕��ꐫ�����ʂ��̗ǂ��V���g���E�X���̏a���|�������킦��B �@�����āAR.�V���g���E�X�̕Ď��L�O���t��i1944�N�j�B�m�C�}�����R���f���T�[�}�C�N�AAKG���}�O�l�g�t�H���A�E�B�[���E�t�B���A���W�[�N�t�F���C���E�U�[���Ƃ��������̑g�ݍ��킹�Ŏ��^���ꂽ���Ƃ����e�[�v�^���ł���B�\�A�����Ɏ����čs���Ă��܂������߃I���W�i���e�[�v�͍s���s���B���ꂪ�u���R�Ɂv���h�C�c�̕����ǂ���_�r���O�e�[�v��������A���Ƃ����̉A������悤�ȃ��m�B���W�[�N�t�F���C���œ��X�Ɩ炵���nj��y��i�́A�����ł����c���������{�P�����Ȃ̂ɁA��̂������肵�����B�܂̍C�ł�������Ƃł���������̏��i�Ə�X�v���Ă����B�Ƃ��낪����������Ƒh�����B�h���t�@���`����ff���Y��ȃE�B�[���E�t�B���̂��́B�c�@���c�X�g�����A�ނ���㔼�̕��ꐫ�����ʂ��̗ǂ��V���g���E�X���̏a���|�������킦��B �@���������܂��́A��Gramophon�̃t���g���F���O���[��BPO�̘^���Ƃ̑����ł���B�����J����ł̃V���[�x���g�h�O���C�g�h�����ȁA�e�B�^�j�A�E�p���X�g�ł̃x�[�g�[���F��No.7&8�̃��C�u�ȂǁA��������D���B���������S���S�����^���ŁA�����Ȃ�ቹ���u���b�Ɩc��ރv���C�Z�����̒j�C���鉉�t���A���ƂȂ��ʔ������Ă���̂����X�������B�������O���C�g�R�y�͂̃����c�̟������̂��Ȃǒ����ƁA�x�������E�t�B���̌������\�����邶��Ȃ��H�Ƃ��������B�x�[�g�[���F���ł͖؊ǂ̃Z�N�V�����̔�ы���ƂĂ��S�n�悢�B�����n�߂̃X�s�[�h�����y�������Ȃ̂��B����ł��ĉ��F�͉�������܂�₩�B���ꂾ���ł������Ȃ̗��̓I�\�����A������ԂŋY��Ėʔ������{������B���̃t���g���F���O���[�̌ÓT�u�������߂Ĕ���������B���Ƃ����ē�������̘^���ŁA�N�����ƌ������Ɩ��^���Ƃ�����A�t���b�`���C�^RIAS���̃o���g�[�N�u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv�ł��A�T�E���h�Ɉ�a�����Ȃ��B���m��������DG�^���͋��ӎ��������āA�Ȃ��Ȃ��T���v�������ȏ�̗ʂ������Ȃ��������A����ŃR���N�V�����̏[���ɓ��ݏo����C������B �@���������܂��́A��Gramophon�̃t���g���F���O���[��BPO�̘^���Ƃ̑����ł���B�����J����ł̃V���[�x���g�h�O���C�g�h�����ȁA�e�B�^�j�A�E�p���X�g�ł̃x�[�g�[���F��No.7&8�̃��C�u�ȂǁA��������D���B���������S���S�����^���ŁA�����Ȃ�ቹ���u���b�Ɩc��ރv���C�Z�����̒j�C���鉉�t���A���ƂȂ��ʔ������Ă���̂����X�������B�������O���C�g�R�y�͂̃����c�̟������̂��Ȃǒ����ƁA�x�������E�t�B���̌������\�����邶��Ȃ��H�Ƃ��������B�x�[�g�[���F���ł͖؊ǂ̃Z�N�V�����̔�ы���ƂĂ��S�n�悢�B�����n�߂̃X�s�[�h�����y�������Ȃ̂��B����ł��ĉ��F�͉�������܂�₩�B���ꂾ���ł������Ȃ̗��̓I�\�����A������ԂŋY��Ėʔ������{������B���̃t���g���F���O���[�̌ÓT�u�������߂Ĕ���������B���Ƃ����ē�������̘^���ŁA�N�����ƌ������Ɩ��^���Ƃ�����A�t���b�`���C�^RIAS���̃o���g�[�N�u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv�ł��A�T�E���h�Ɉ�a�����Ȃ��B���m��������DG�^���͋��ӎ��������āA�Ȃ��Ȃ��T���v�������ȏ�̗ʂ������Ȃ��������A����ŃR���N�V�����̏[���ɓ��ݏo����C������B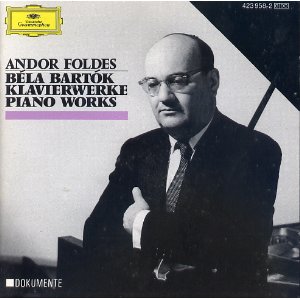 �@���Ȃ݂ɓ���DG�ł��s�A�m���͍X�ɋ����ȃJ�}�{�R�����ł���B�茳�ɂ���̂́A�t�H���f�X�̉��t����o���g�[�N��i�W�ł��邪�A�n�m�[�t�@�[�E�X�^�W�I�ł̂��̊ۂ܂����������͂ǂ����Ă���a�����ʂ����Ȃ��B�O�[���h�̃A����������������Ȃ��B�����A���͂ȃn�C�J�b�g�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A���R���킩��Ȃ��B�v�����ē��̓g�����X��Lessen�Ђ�Hypernik
Transformer�ɕς��Ă݂�ƁA������j�ɂ����x�[�[���h���t�@�[�̂悤�ȉ����ɂȂ�A�قǂ悢�����Ɏ��܂����B���̉����𗊂��UTC C2080�ōēx�������Ă݂�ƁA���낤���Ƃ��A�C�R���C�U�[���t���b�g�̏�Ԃ�OK.�B�܂�4�`8kHz�̍��悪10dB�قǑ���Ȃ������i�������̓��[���I�t���Ă����j�̂ł���B�����X���́A�M�[�[�L���O��1950�N�Ɍ̋��̃��W�I�ǂœ��ꂽ�o�b�n�̃p���e�B�[�^�W�ł������āA����ŃP���y�̃x�[�g�[���F�����S�W�ɂ����X�Ǝ���o����Ƃ������́B�y���݂��������B �@���Ȃ݂ɓ���DG�ł��s�A�m���͍X�ɋ����ȃJ�}�{�R�����ł���B�茳�ɂ���̂́A�t�H���f�X�̉��t����o���g�[�N��i�W�ł��邪�A�n�m�[�t�@�[�E�X�^�W�I�ł̂��̊ۂ܂����������͂ǂ����Ă���a�����ʂ����Ȃ��B�O�[���h�̃A����������������Ȃ��B�����A���͂ȃn�C�J�b�g�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A���R���킩��Ȃ��B�v�����ē��̓g�����X��Lessen�Ђ�Hypernik
Transformer�ɕς��Ă݂�ƁA������j�ɂ����x�[�[���h���t�@�[�̂悤�ȉ����ɂȂ�A�قǂ悢�����Ɏ��܂����B���̉����𗊂��UTC C2080�ōēx�������Ă݂�ƁA���낤���Ƃ��A�C�R���C�U�[���t���b�g�̏�Ԃ�OK.�B�܂�4�`8kHz�̍��悪10dB�قǑ���Ȃ������i�������̓��[���I�t���Ă����j�̂ł���B�����X���́A�M�[�[�L���O��1950�N�Ɍ̋��̃��W�I�ǂœ��ꂽ�o�b�n�̃p���e�B�[�^�W�ł������āA����ŃP���y�̃x�[�g�[���F�����S�W�ɂ����X�Ǝ���o����Ƃ������́B�y���݂��������B�@���Ȃ݂ɃE�B�[���E�t�B���̖��R���}�X�̃V���i�C�_�[�n����1953�`55�N�Ɏ��^�������[�c�@���gVn�\�i�^�W�ł́A���@�C�I�������������������I�P���Ɠ����o�����X�ŁA2.5kHz�ȏオ-6dB�ŗ��������B�V���i�C�_�[�n����t�H���f�X�́A���t���E�l�C���Œn���Ȃ̂ɉ����A�^���̈�����������ĕ]�����Ⴂ�̂ł���B�R���T�[�g�ʼn̂��鉉�t�ł͂Ȃ����߁A�����������̃��b�X�����Ă���悤�Ȋ��������Ȃ��͂Ȃ����A�x�[���^BPO�̉��t���D���Ȑl�Ȃ�A�����̉��t�Ƃ��]�~�Ɏ����X���đ��͂Ȃ��Ǝv���B �@���ꂪDecca���^�̃N���E�X�^VPO�ɂ���̌��u��������v�ƂȂ�ƁA�܂�ł���グ�ł���B�̎�w�͈�a���Ȃ����A���̉��ň���������B���Ƃ�����EMI�̊�̌��u�����[�E�E�B�h�E�v�͑��v�ł���B�����ADecola�̂悤��PX25�̑������̐^��ǂŗ��蒼���Ȃ��ƃ_���Ȃ̂��낤�B�����Ȃ�ƃO�����t�H���́~�ł���B���Ƃ����ē����p���ł�EMI�̊�̌��u�����[�E�E�B�h�E�v�͑��v�ł���B�Ȃ�Ƃ����ߍ��ȃI�[�f�B�I�̐��E���낤�B  �@���ƕ��ނ���┻��ɂ����^���ɁA���ƃV�����v���b�e���n�̏@���Ș^��������B���m�������ł́A1954�N�Ɏ��^�����M�����^�[�E���~���Ɛ��g�}�X����̑��̃��n�l���ȂȂǂ�����A���Ȃ��݂̃��C�v�`�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�̂ق��A��̃��q�^�[�ՂŖ��G���@���Q���X�g�߂�w�t���K�[������ȂǁA�V���̐w�c����������s�v�c�ȃZ�b�V�����ł���B���Ƃ��ƃ��~�����́A1930�N��̃h�C�c�E�I���K�������^���̒��S�I�l���ŁA���݂̃o���b�N�E�I���K���̕ۑ��ɑ傫����^�����B���̈Ӗ��ł́A���t�ƂƂ��Ă��̓h�C�c�@�����y�̕��������A���ۂɃJ���g�[���߂Ȃ���v�������Ƃ�������B���Ƀi�`�X�̌�ɋ��Y���ɑg�ݓ������Ƃ����Q�d�̋��̎���ɁA�o�b�n�䂩��̐��̑����ێ����悤�Ƃ��邽�߂ɕ������㏞�͑z����₷����̂Ǝv����B���̋M�d�ȃh�L�������g�����A�{���͋��e���t���P���̗�������ށA�J�b�`���������̌X���̂͂������A�ш悪��⋷���̂ƁA�����̍L���芴���o�Ȃ��_�ŁA�u�X�e���I�łȂ��̂��ɂ��܂��v�Ƃ��������悭�������^���ł�����B�����EL84�{Baronet�ōĐ�����ƁA����̊Â݂ƍ����̔��������������g�[���Ɏ��܂�B���N�����c���g�}�X����̍����V���˂������銴�����ǂ��o�Ă��邵�A�Ə��Ƃ��Ȃ�Ό��݂̂��̂ƑS�����F�Ȃ��B���ʂ��ғ����������Ƃ������ؓI�ȃ��n�l���Ȃ��A�ǎ��ȃ��W�I�E�h���}���Ă���悤�ɓW�J����B �@���ƕ��ނ���┻��ɂ����^���ɁA���ƃV�����v���b�e���n�̏@���Ș^��������B���m�������ł́A1954�N�Ɏ��^�����M�����^�[�E���~���Ɛ��g�}�X����̑��̃��n�l���ȂȂǂ�����A���Ȃ��݂̃��C�v�`�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�̂ق��A��̃��q�^�[�ՂŖ��G���@���Q���X�g�߂�w�t���K�[������ȂǁA�V���̐w�c����������s�v�c�ȃZ�b�V�����ł���B���Ƃ��ƃ��~�����́A1930�N��̃h�C�c�E�I���K�������^���̒��S�I�l���ŁA���݂̃o���b�N�E�I���K���̕ۑ��ɑ傫����^�����B���̈Ӗ��ł́A���t�ƂƂ��Ă��̓h�C�c�@�����y�̕��������A���ۂɃJ���g�[���߂Ȃ���v�������Ƃ�������B���Ƀi�`�X�̌�ɋ��Y���ɑg�ݓ������Ƃ����Q�d�̋��̎���ɁA�o�b�n�䂩��̐��̑����ێ����悤�Ƃ��邽�߂ɕ������㏞�͑z����₷����̂Ǝv����B���̋M�d�ȃh�L�������g�����A�{���͋��e���t���P���̗�������ށA�J�b�`���������̌X���̂͂������A�ш悪��⋷���̂ƁA�����̍L���芴���o�Ȃ��_�ŁA�u�X�e���I�łȂ��̂��ɂ��܂��v�Ƃ��������悭�������^���ł�����B�����EL84�{Baronet�ōĐ�����ƁA����̊Â݂ƍ����̔��������������g�[���Ɏ��܂�B���N�����c���g�}�X����̍����V���˂������銴�����ǂ��o�Ă��邵�A�Ə��Ƃ��Ȃ�Ό��݂̂��̂ƑS�����F�Ȃ��B���ʂ��ғ����������Ƃ������ؓI�ȃ��n�l���Ȃ��A�ǎ��ȃ��W�I�E�h���}���Ă���悤�ɓW�J����B�@�����X���̘^���Ƃ��āA�}�E�G�X�x���K�[������h���X�f�����\���ˍ����c��1950�N��̕����^�����A1960�N��قǍ|�S�̏��x���オ���ĂȂ����A�˂�������悤�ȏ��N�����̈����͊��ɂ��̂̕З��f����B������傫�Ȏ��n�������B �@�����̉�������ɂ���̂��A�����̋����Y���̘^���ŁA�\�A����ʂ̃e�[�v�^����ڎ����Ă�������ɁA�{���Ńe�[�v�^���������Ɠ������x���Ŏ��p�����ꂽ�̂�1950�N�����炾�����炵���B���傤�Ǘǂ��T���v���́A�S�����m�t�^���X�N���������ɂ��X�N�����[�r�������ȏW�B�ŏ��̂R�Ԃ�1946�N�ŁA�������ɂ����SP�^���ł���B1948�N�̂P�Ԃ̓O���[�]�[���ŁA�����炭�e�[�v�^�������A�}�C�N�͋��\�A���̂��߉����������Ȃ̂��낤�B1950�N�̂Q�Ԃł悤�₭Hi-Fi�ɒǂ����Ă���B���Ȃ݂�1947�N�̃l�E�K�E�X�ɂ��X�N�����[�r���̃s�A�m�ȏW���A�����W�͋����̂Ƀm�C�Y���Ȃ����߁A�\�A���}�C�N�ɂ��e�[�v���^�Ǝv����B1956�N�̃��X�g���{�[���B�`�^�V���X�^�R�[���B�`�ɂ��`�F���E�\�i�^�̘^����Hi-Fi�K�i�ł���B1950�N��Ƀ^�[���b�q���ӔN�Ɏc�����`�F�R�E�t�B���Ƃ̈�A�̘^�����A�h�C�c�̃e�[�v�^���Z�p�̉��b�������̂̂ЂƂ��B�����1949�N�̃X�[�N�g�ȁu���Ƃ��b�v�A���i�[�`�F�N�u�O���S�����E�~�T�v�i�o�J���^�u���m�������j�̓����W�������B�����𑍍�����ƁA1946�N�܂ł̓��b�J�[�ՁA1947�`49�N�̓e�[�v���^�����}�C�N�͋����i�A1950�N����m�C�}���^�̃R���f���T�[�}�C�N���g�p���ꂽ�l������B����ł����ɐ旧���h�C�c�Ř^�����ꂽ�A1947�N�̃��@���q���ɂ��o�b�n�E�I���K���W�A1948�N�̃h���X�f���ŏ��N����̃V�����C�A�[�̐������^�����^���́A���炩��Hi-Fi�^���ł���B �@�y�[�W�ŏ��� |
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
